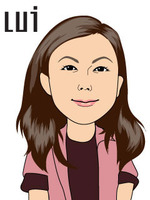2009年01月25日
登美の丘ワイナリー ワイン飲み比べ
 2008年06月14日(日)
2008年06月14日(日)今回の 「 技師長が語る特別ワイナリー・ツアー 」参加者達の本当のお目当ての試飲会にいよいよ突入です。
ドイツのホイリゲみたいな長いテーブルが並んでいる部屋に案内されました。
席割りは既にワイナリー側が決めており、指定された席に誘導されました。
二へドンは講師に1番近い側でした。
1口ワインを試しては、水で口を漱ぐのが正しいテイスティングの方法なので、
ミネラルウォーターのペットボトルも置いてありました。
今回は全部で6種類のワインを試飲します。
既にテーブルの上には6つのワイングラスが置かれ、それぞれのグラスにはワインが注がれておりました。
では1種類ずつ、特長を書き綴ってみますね。
1.「 樽醗酵 甲州 2005 」 ( 白 )
2005年は、雨が少なく、気温は平年並み。
このブドウは棚栽培で、収獲時期は遅く収獲した。
薄~い色です。 同じ白ワインでも、違う種類の入っているワインの
グラスを並べてみると、色が全く違うのに驚かされます。
この白ワインは若干、緑がかっています。
香りは華やかです。
樽の香りが混じって、みかんの香りみたいに感じました。
例年、ライチの様な香りがするらしいのですが、
この年は、みかんの香りが強く出ました。
同じ銘柄でも製造年によって味に変化が出る。 ワインの醍醐味ですねー。
技師長からのアドヴァイス 「 ワインは口の中に残る味わいを楽しんで下さい。」
へえ~。 ワインの液体の味そのものを楽しむのでは無いのね?
では早速、口の中に何が残ったか・・・・・・・
口にワインを入れた瞬間は柔らかく、その後、酸味が残ります。
「 甲州 」という銘柄は、渋く、ポリフェノールが高いとの事。
二へドンが、この試飲会で1番驚いたのは、一口に白ワインと言っても、
色味が全然違うという事です。
緑ワインや黄色ワインや透明ワインだって有り得ます。
赤ワインでなければ、全部 「 白ワイン 」になってしまう所が大雑把で良いですね?
2.「 登美の丘 2005 」 ( 白 )
このワインの創り手が意図した物は、「 柔らかさと、キリッとした物を混ぜる 」
だそうです。
ああ、やっぱり良いですよね。 お店で売られているワインを買うだけだと、
創り手の意図までは把握出来ないですものね。
技師長さんの解説では、「 地味な澱んだ様な香りが特長 」で、
「 グラスを揺すって混ぜると、香ばしさが出て来る 」 そうです。
早速、グラスを揺すって試してみましょう。
うわ、本当だ! 口の中に長く入れていると味が変わって来ました!
ワインをゴクゴク飲んでしまったら、ワインの味は理解出来ないという事なんですね。
貧乏臭く(!?) いつまでも口の中でねぶっていると、味の変化が楽しめる。
分かりましたよ。 ワインの極意が。
「 ワインは、時間を味わうもの也。」 ← すっかりその気のアタシ。
3.「 登美 2005 」 ( 白 )
2005年 棚栽培のブドウから作ったワインで、凝縮した果実の味わいが楽しめる。
色は黄色味が強く、黄金色と言った方が近いかも。
新しい樽を17%使用しています。
セレブの香りがポイント。 まろやかで、口当たりが滑らかだが、口の中に酸味が残る。
熟した果物由来の味のワイン。
4.「 登美の丘 2005 」 ( 赤 )
赤ワイン特有のツンとした匂いがある。
新しい樽を45%使用。
仄かな杉の香りがする。 別の人に言わせると「 鉛筆の削りカスの臭い 」!?
口当たりは軽いと思いましたが、
技師長さんの解説では 「 比較的に濃い、強い、骨格の有るワイン 」だとの事。
2004年物は、もう少し柔らかい味になっているそうです。
5. 「 登美 2004 」 ( 赤 )
2004年というのは、甲府で気温40.4℃を記録した猛暑の年だったそうです。
9月16日に調べた時に、26.39糖度を記録しました。
多分1番糖度が上がった年だったらしいです。
樽熟成で16ヶ月寝かせた物です。
この樽は、フレンチオーク 93%に、アメリカンオーク 7%が使用されています。
このワインの特長は、「 すっきりした香り 」です。
確かに、実際に飲んでみると、物足りない位の軽さだけれども、味が舌に残ります。
ワインの味にボリュームが有って、渋みが残ります。
もっと熟成させれば、もっと美味しくなるそうです。← 皆さん、メモして。 メモ! メモ!
6.「 カベルネ・ソーヴィ二ヨン 1987 」 ( 赤 )
1987年は、1番雨が少なかった年です。
登美で1番沢山「 登美 」ワインが出来た年でも有ります。
醗酵中に、酸素を与えず、そのまま放置プレイをしたそうです。( 笑 )
このワインは面白いですよー。 人によって、様々な表現をします。
曰く 「 煙草の葉の香り 」 「 ブランデーの様な香り 」 「 枯れ葉の様な香り 」。
ワインを揺らして混ぜると、土や草の匂いがします。
刺激が有る、スモーキーな味です。
二へドンはこのワインの味が1番気に入りました。
複雑な味が、メッチャ面白い!!
残念ながら、非売品のワインです。
ワインマニアの皆さん、ごめんなさいね。
悔しかったら、皆さんも、サントリー登美の丘ワイナリーのツアーに参加してね!!
一通り、解説を聞きながらの試飲が終わった後、質疑応答になりました。
最初の質問者が貴腐ぶどうを意図的に作る事は出来ないのか? という質問をした所、
参加者の大半が貴腐ぶどうに興味が有ったらしく、この話題で持ちきりになってしまいました。
「 貴腐( きふ )ぶどう 」って何?
白ワイン用品種のふどうにおいて、Botrytis cinerea ( ボトリティス・シネレア )という菌(黴)が
果皮に感染する事によって糖度が高まり、芳香を持つ様になる現象です。
で、この貴腐ぶどうを意図的に作れるかどうかですが、技師長さんの答えはこうでした。
「 貴腐が出し易い環境を作ってあげると、出せる。
但し、赤ぶどうに付くと、赤色の色素を破壊してしまうので、
そのリスクを負ってまで、わざわざ意図的に作り出す意義が有るかどうか。
また、貴腐を出現させるには複雑なコンディションが必要なので、
毎年意図的に出来る訳では無い。
ただの病気のワインになってしまっては、意味が無い。 」
つまり、貴腐ぶどうは、偶然に出来るのを待つからこそ、レアな価値が出るという事でしょうかね。
意図的に貴腐を作るのは邪道という事ですかね。
技師長さんが総括としてまとめた話は、
「 ブドウを植え付ける時に、ワインの味を考えて作付けをする。
メルロは、最初のボリュームは有るが、後半は無くなってしまう。
カベルネは、後半のボリュームが強い・・・ 等。 」 でした。
何事もそうですけど、ワインを知れば知る程、奥が深くて、嵌まりますね。
もっと体験してみたいワインを知る1日でした。
***** 「 登美の丘ワイナリー ワイン飲み比べ 」 ・ 完 ********
小鹿野ワーケーションツアーリポート ~ 旭通りを歩いてみた。
小鹿野ワーケーションツアーリポート ~ 小鹿野の路地巡り。
街で出会った気になる看板3連発!
独鈷の湯公園
宇奈月温泉に行ったら是非歩いてみたい「 やまびこ遊歩道 」。
「 湘南クッキー 」見~つけた!!
小鹿野ワーケーションツアーリポート ~ 小鹿野の路地巡り。
街で出会った気になる看板3連発!
独鈷の湯公園
宇奈月温泉に行ったら是非歩いてみたい「 やまびこ遊歩道 」。
「 湘南クッキー 」見~つけた!!
Posted by ニヘドン at 00:32│Comments(0)
│そぞろ歩き
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。