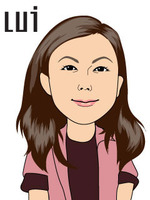2010年03月01日
ある絵描きの作品に関する考察
 今日は前から気になっていた
今日は前から気になっていた或る絵描きの作品を
酒の肴に色々ゴタクを
並べてみようと思います。
その作品と言うのは、2009年12月26日(土)のジャパノイズオーケストラのフライヤーだったのです。
何が気になったのかと言うと、見れば見る程に不思議な絵だからなんです。
ニヘドンは絵や彫刻やアートを見るのは、普通に好きでして、
美術館通いは高校生の時から始めました。
1枚1枚の絵の前に立ってじっと眺めていると、作品との対話が出来るのが
美術鑑賞の幸福のポイントです。
書籍や映画は、どうしてもストーリーを追って行ってしまう。
ところが美術作品は基本的には動かないので、無制限にボーっと見ていられる事が出来るのです。
それこそ、朝一番に美術館に入って、係員に追い出される閉館時間まで見入っていても良いのです。
二へドンが美術館通いが好きなのは、対象物が動かないだけに、思いっきり我が儘な鑑賞が出来るから。
絵には色々な種類が有ります。
音が聞こえて来るもの。 音が無い世界が広がるもの。
絵の中を風が吹き抜けるもの。 空気の動きの無いもの。
太陽光線をいっぱいに浴びたもの。 夜の帳( とばり )が下りたもの。
生の世界を描いたもの。 死の世界を描いたもの。
1枚の絵から感じる物は様々です。
人間に一目惚れをする事が有る様に、作品を見た瞬間に「 あ、この絵、好き! 」って思う事が有ります。
思えば二へドンは、小説家や音楽家は、1度気に入った人はずっと長く追いかける習癖が有ります。
が、画家やアーティストの場合、人間を追いかける事は今までありませんでした。
その画家本人と言うよりも、1点1点の作品が好きかどうかで判断するようです。
なので、ムンクが好きかどうかは、微妙なのです。
彼の初期の作品の「 墓場のマドンナ 」 や 「 叫び 」は大きく支持をする作品ですが、
彼の50歳以降の作品は、全然興味すら惹き起こしません。
ムンクは長生きをした画家ですが、二へドンに言わせると彼の50歳以降の作品は駄作ばかりです。
ムンクの作品の中で大好きなものも有るし、大嫌いな作品も有ります。
ムンクの全作品の中では、二へドンの気に入らない作品の方が数が多いので、
ムンクが好きかどうかって・・・・・・・・・・・・言えないなあ・・・・・・・・・・。
こんな二へドンが、ジャパノイズオーケストラのフライヤーを一目見た時に
二へドンは思いました。 「 あ、この絵好き。」
じゃあ、どんな所が好きなのか、じっとこの絵を見詰めると・・・・・・・・・・・・。
ありとあらゆる物が詰まっているので、頭がくらくらしてしまいます。
大きな特徴は色遣いです。
赤や黄色やオレンジと言った強烈な印象を与えるどぎつい色を使った面積は微々たるものです。
ゴーギャンやゴッホの絵に比べると、色彩は大人し過ぎる程です。
だからと言って、この絵の前を通り過ぎようとする貴方。 ぶんぶんぶん!
よく見てやって下さいよ。
まず、両端に、上から枝垂れている塊がありますよね。
これは両方とも、基本的に白色、水色、薄緑色が使われています。
でも右側に1箇所だけ、やや濃い目の紫色の部分が有ります。
左側にも1箇所だけ、濃い紫色の部分が有るのです。
二へドンはこれに頭をガツンと打たれました。
「 何故1箇所だけ? 」
普通の人間だったら、1回使った色を、後もう1回か2回、どこかに使いたくなると思うのですが・・・。
二へドンはフラワーアレンジを10年以上習っていて、色の配色にはちょいとウルサイのです。
色彩検定なんて云うものを受けてみようと思う位。
ああ云う風に、細かくパーツが分かれている部分に、1箇所にだけ違う色を使うと言うのは、
そしてそれが浮いていない、いや、むしろ逆に気がつかれない程にひっそりと息づいているのには驚嘆!
もしこれを、絵描き自身が意識的に行なっているとしたら、かなりなテクニシャンだし、
逆に無意識にやっているとしたら、天性の色彩マジシャンだと思います。
この様に「 1箇所だけ違う部分 」が、随所に現れているのです。 この絵ときたら。
裸身の少年の背後には大きな顔が笑っています。
カフカの小説「 変身 」の芋虫にも見えるし、
スタジオジブリのアニメ「 千と千尋の神隠し 」の「 かおなし 」の類の妖怪にも見えます。
この顔の下は茶系のラインが流れています。
この茶色の部分は隆起した地面かもしれないし、川の流れかもしれないし
( この様な「 顔 」が出現する位だから、川が普通の水の色をしていなくて当然だと思う。)、
案外とこの「 顔 」の髪の毛なのかもしれません。
この茶色の部分は、幾つも筋が入っていて、それぞれ違う色のトーンに塗り分けられています。
1筋だけこげ茶色の部分が有ります。
二へドンがこのこげ茶色を使うとしたら、きっと無意識に中央に置くと思います。
だって1箇所だけ使うのですから、中央に置くのが1番安定しませんか?
2箇所使うのだったら両端という考え方も有りますが・・・・・・・。
それがこの絵では、こげ茶のラインが中央より少しずれた場所に使われているのです。
これが凄く意味有りげで、二へドンは12月よりずっと、この謎を解こうとして絵を眺めるのですが
未だに答えは分からずじまい。
この茶色のラインは、右上から左下に斜めに走っています。
このラインの流れに逆らうように黄緑、黄、黄緑の3色のラインがほんの短いラインですが
茶色のラインに直角に交わる角度で描かれているのです。
普通、この短いラインは描かないでしょう?
でもね、この黄色の短いラインが、この絵全体を引っ張り上げている大黒柱なのだと感じます。
左下の草も、3本だけ、他の草のラインと直角に交わる様に描かれています。
この絵は一見、プリミティブな幻想の世界の形を取っていながら、
交差し合うラインや、どこかに調和を乱す仕掛けを幾つか仕込みながら、
「 不調和のバランス 」を保っています。
この絵の下には実は21世紀の現代社会の顔が覆い隠されているのではないでしょうか?
そう思うと、ラインの交差が高速道路の立体交差にも見えて来ます。
2010年03月01日
「 身体で語るバレエのストーリー 」
 第75回舞台芸術講座
第75回舞台芸術講座「 身体で語るバレエのストーリー 」
日時 : 2010年01月30日(土)
会場 : 神奈川県民ホール 小ホール
講師 : 小山久美
( スターダンサーズ・バレエ団代表 )
料金 : 一般 ¥2,000.-
学生 ¥1,500.-
( 全席指定 )
********************************
目の前に小山久美さんが登場しました。
背かスラリと高くて、手足が長くて、
ダンサーとしての現役を退いたとは言え、
あのプロポーションを維持しているって、
凄い事です。
二へドンはただただ、口ぽか~んと小山さんを見詰めるだけ。
小山さんは、落ち着いたトーンの声で、森の中のコケの下から水が少しずつ滲みてくるような
ひそやかな話し方で話を進めて行きます。
「 子供の頃バレエを始めて、そのままずっとバレエ団と関わっています。
踊りからは引退しましたが、バレエ団に関わって現在に至っています。
私は踊っている時からドラマが好きだったので、今日は
『 身体で語るバレエ 』をお話したいと思います。
皆さんがこれからバレエを鑑賞する時のお役に立てればいいなと思います。
バレエは言葉を使いません。手振り、身振りでストーリーを伝える事、所謂ジェスチャーを
バレエではマイムと言います。
19世紀に生まれたバレエが、皆さんのお近くに有ると思うのですが、
マイムにはある程度知識が必要であると思います。
腕をしっかり上げ、手のひらを正面に向けます。 」
小山さんが実演をしながら解説をしてくれています。
小山さんは身体にフィットするシンプルなロングドレスで、現役バレリーナでまだまだやれそうな
雰囲気ですよ。
「 かなり節不自然です。
( この動作を )自然にやると、肘は曲がってしまうのが普通です。
腕を使う時にリズムが必要です。
踊る時だけではなく、マイムにもリズムが音楽的でなければならないのです。
そこでマイムだけの練習を何度も何度もしています。」