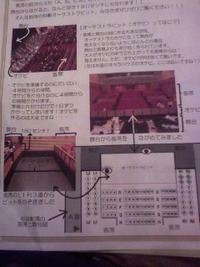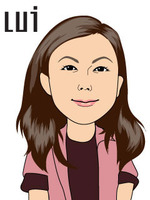2008年01月12日
1月のヴァイオリン・レッスン
 2008年01月11日(金)
2008年01月11日(金)ヴァイオリンレッスン46回目。
レッスンを始めて67週目。
年末年始が入ってしまったので、
前回のレッスンから20日振りのレッスン。
教室に通う感覚が薄れ、
「あれ? 今日レッスンあったかな?」って思ってしまう。
まずは一人ずつ調弦を先生に見てもらう。レッスン1年目は、「お願いします。」とヴァイオリンを先生に差し出せば、調弦は全て先生にお任せであった。2年目の今は、「調弦位、てめぇでやりやがれ!」モードに入った。
レッスンが休みの間、乾燥する冬にも関わらず、音は、そう酷くは狂わなかった。そう、うちの泰次郎君は、滅茶乾燥に弱いのである。
音の狂いが少ないけれど、調弦の練習と思って毎日少しずつ弦を自分でいじってみた。一昨日、少しやり過ぎでしまった。どうにも音が合わないのである。合わないと言う事はわかる。でも、じゃあどうしたら良いかが分からない。仕方が無い。後2日で先生に見てもらえると思い、狂った音のまま練習した。
今日、先生の指導を受けて分かった。基本のA線が高かったのである。それで他の線まで悪影響が出てしまったのである。
まずはA線を調整。先生がアジャスターを回せと仰る。回す。まだおっかなびっくり状態で回してしまうので、先生からは「もっと、もっと!」と指示が飛ぶ。余り時間がかかるので、先生がニヘドンの所までやって来てアジャスターを回す。「あら、もういっぱいで、これ以上回らないわね。」そしてニヘドンが弓を引いて音を出している間、先生がA線の糸巻きを動かして正しい音に調整してくれました。それから先は、又「調弦位てめぇでやりやがれ」モードに戻り、先生は言葉で指示を出すだけ。自分で何とかしないといけない。
次のD線は、自分で糸巻きをちょっと動かしただけで先生のOkが出た。ふー。いつもこの位簡単だと良いのに。次に一番太いG線。このG線には毎回泣かされる。G線の糸巻きがすぐ緩んでしまい、ちょっと糸巻きに触れただけで、糸巻きが2回転も3回転も回ってしまい、弦はデロデロに伸びてしまうのである。今日も先生の指示通り糸巻きを回していると、糸巻きの野郎、回転を始めた。すかさず混身の力を左指に込めて糸巻きを押さえ込んだ。ニヘドンのピンチをイチ早く察知した先生がニヘドン救出に乗り出してくれた。こうなったら、後は先生にお任せなのである。ふー。最後のE線はOkだったので、本日のニヘドンの調弦は、これにて終了。
次にもう一人の生徒、最後にもう一人の生徒と順々に先生がみて下さる。
3人全部の調弦が終わるのに掛かった時間は、きっかり10分。お高い月謝のレッスンで失う10分は超辛い。どのみち調弦も覚えなければならないのですが。
因みに今月からクラス名が「アドバンス・クラス」になったら、月謝が 9,450円から 10,500円に値上がりした。一回のレッスン料が3,500円か。石田様の演奏会のチケット並みだな。やれやれ。
テキスト2冊目のレッスン1。 まずはC Major Scale の練習。今までの Scale練習 と違うのは、ドの音からスタートする事。
今まではスタートの音の指は0か1だった。今度は3の指からスタートするので次の音がすぐ隣りのD線に移らなければならない。案の定、先生からの指摘は、「移弦の準備は早めに!」でした。ヴァイオリンは、常に先の事を考えて準備を怠りなくしなければならないので、3歳から習ったら、石田様みたいに几帳面な男の人に育つと思うよ。
今日のイメージトレーニングは、移弦をした時の脇の動き。小手先だけで移弦をするのではなく、脇をどんどん下げて行くのを弓の角度と共に体感する。
次に弓を持ったつもりで右腕を動かしながら左手を背中側に回し、肩甲骨を触る。肩甲骨が動いているのを確認する。今度は逆に左手で弦を押さえているつもりになって指をごにょごにょ動かしながら右手で左の肩甲骨を触る。これも又、肩甲骨が動いているのを確認する。 つまり、腕は腕の付け根から始まるのでは無く、肩甲骨が腕の始まりである事を認識せよとの事。
ヴァイオリンを弾く時は、肩甲骨から動かして弾けと、そういう事なのでありました。
2冊目のテキストでは、新しく Chord のコーナーが出現。 前回のレッスンで行なった Cコードをもう1度練習。
芳しく無い。ミ の音が下がっている。 新しく Fコードも練習する。 これはもう悲惨な事になりました。 それぞれの線で、
2と3の指が交錯するので、ミス連発。 無意識に指が動く様に叩き込まなければなあ・・・・。
Exercise は、家で練習していたのより、メチャ テンポが速く、あせった。 4の指(小指)をうんと遠くに置かなければならない
高いドの音がネックになる。 小指を置く時に、横方向から置こうとすると無理なので、指板の上を通って置く様にしなさいと
注意を受ける。 これが 「 はい、そうですか。 」 と簡単にいくものではないのである。
今日はさらに、主音をはっきり弾くように指示される。 これもね、テンポが速い中で一体どうしたらいいねん?
新しい Exercise の曲も練習した。 これは4小節の短いものだが、 人差し指と中指をくつけ、少し間を空けて薬指と小指をくっつけると言う新しい指のパターンなのである。 妖怪人間ベラにでもなった様な気分です。
これも家で特訓しなければ追いつかないと思う。
そしてハイドンのセレナーデ。 一応先生からは、「 よく弾けています。」 と言うコメントを頂きました。
が!! やはり高いドの音に問題有り。 弓は、長いスラーでも弓を全部使わないように注意された。
ドイツ物を弾く時の基本なのだそうである。 弓を細かく動かし、弓を弦にしっかり乗せるのが大事だとの事。
「 来週は強弱をつけて演ってみましょう。」 だそうである。
「 レパートリー集 」からは サティの 「 ジュ・トゥ・ヴ 」。 これも一通り全員で通して弾いてみた後、先生の指示を受ける。
サティはフランス物なので、さっきのセレナーデとは異なり、弓は大きく元まで使うんだそうである。 フランス物は、音の中に空気を入れる様に弾くのだとか。 「 え!? 先生!! 音の中に空気って、入るんですか!! 」
いや、喩えだって言う事は分かるのですが・・・・。
この曲の難しい所は、弓のアップとダウンのバランスが不揃いなんですね。 人間にとって、一番楽なのは、2拍アップにしたら、2拍ダウンにしたら、超楽なんですよ。 或いは3拍アップにしたら、3拍ダウンにするとかね。
この曲は4拍ダウンにした所で、2拍でアップしなければならないので、ダウンの時のスピードの倍の速さでアップしなけりゃ
ならないのですよ。 その時には、手だけの力でアップさせようとしないで、手首と肘の中間で押し上げる様にしろとアドバイスを頂きました。
C Major から G Major に転調するのも、ミスを誘発させるし、こりゃまた練習だなあ・・・・。
でも家で練習している時よりも、教室で伴奏君の伴奏付きで弾く方が、断然楽しかった。
家に帰ってから、先生の注意に従って、弓を全部使うように弾いたら、すっごく気分が良かった!!
また来週のレッスンも頑張ろう!!
2008年01月18日(金)
ヴァイオリンレッスン47回目。
レッスンを始めて68週目。
レッスンの準備は、1人1人の調弦から始まる。
冬場は乾燥して、ヴァイオリンの木が縮み、糸巻きが緩みやすくなる。
今日も3人の生徒の調弦に、10分強の時間がかかってしまった。
先生からのアドヴァイスは、
「 調弦の時間を短縮するには、弦をはじいて、大体の音の目安を立てる。
余りにも狂っている時は、糸巻きを目分量で動かしておく。」
と言う事でした。
「 もう良い加減に、調弦位、自分達でパッパッとやりやがれ!!」 と言う
先生の内なる声が聞こえて来る気がした。
まずは、C Major スケールを練習した。
1. 1つの音を3拍ずつ伸ばす。
2. 少しテンポを速めて、1つの音を3拍ずつ。
3. 中弓で、1つの音を3回ずつ弾く。( ドドド、 レレレ、ミミミ・・・という感じ。)
4. 2つずつスラーをつけて。
5. 4つずつスラーをつけて。
今日、二へドンは4つスラーの練習でしくじりまくった。
しくじりまくって、他の2人の生徒に全然ついていけなかった。( 涙 )
1回躓くと、立ち直りが遅いのが、二へドンの弱点なんですね。
これって、練習で克服できるものなのですかね?
1週間みっちり練習しないと駄目じゃの~。
曲の練習の方が楽しいもので、つい、基本のスケール練習を疎かにしてしまうのだ。
コード練習は、Cコードのみで終わってしまった。 あら?
先週やったFコードは、今日はやらないのかな?
4つスラーで滑りまくったのに、それでもまだFコードをやりたい二へドンであった・・・・。
新しいテキスト(2巻目)の3ページのエクササイズを行なう。
まずは、①。 12小節で、E線の高いCの音を4の指(小指)で抑える箇所が随所に出て来る。
音程は必ずしも正確には出来なかったが、先生からの音程の指摘は無かった。
が、二へドンは、弓の入り方が鋭角的過ぎると、再三の注意を受けてしまった。
直したいのは山々なのですが、もう1年以上、これで弾いて来てしまっているので、
なかなかどうして、はい、そうですか・・・・・と言う訳には身体が動いてくれない。
先生の最後のコメント。 「 スラーも出来ているので、これはもう良いでしょう。」
ああ・・・・・・また不完全燃焼で終わるのか・・・・・・・・。 ガックシ。
次は、1つ飛ばして③。
家での練習はOKだと思ったが、フォームの事を細かく指摘された。
・ 左手小指を縮めない。
余分な力が入っているから、小指が縮まる。
小指がいつもリラックスして、伸びている様に手首から力を抜く様に。
でも、力を抜こうと手首を意識すると、余計に力が入ってしまったりしません?
・ 弓を持つ右の手首も柔らかく脱力して。
・ 移弦の角度が急過ぎる。
隣の弦に移弦する時は、隣の弦の内側を使うように。
ヴァイオリンは、どこまでも合理的に頭を使わなければならないのですね。
O型人間の二へドンには、なかなか厳しい世界なんです・・・・・。
新しく、1つ戻って、②の練習に入った。
これは家では全く予習が出来なかった。
と言うのも、この曲は重音の練習曲なのである。
16小節の中に、上げ弓の二重音が4回、下げ弓の二重音が2回、
6拍伸ばす二重音の中に、弓を下げから上げに返すものが1回、
そして三重音が1回出て来る。
重音の弾き方が全く分からなかったので、
( 自己流でやって、変な癖をつけたくなかった。)
家では全く予習が出来なかったのですが、先生の指示通りやってみた。
まずは、上の音だけを出してみる。 次に下の音だけ出してみる。
それぞれの単音を確認した後、下の音を出して、そのままちょっと弓の角度を
動かして2本の弦を弓でこすったら、綺麗な重音が出来た!
さすが、先生に習うと話は早い!!
1人で楽譜を見て、理解しようと悪戦苦闘していた自分が馬鹿みたい。
そして、目からウロコだったのが、三重音の弾き方!!
お恥ずかしながら、二へドンは今まで三重音は、1度に3本の弦をこするんだと思っていたのだ。
試しに家で1人で試行錯誤をしてみたが、全然出来なかったのだ!!
先生が仰るには、難曲には四重音も出てくるらしい。 うひょ!!
先生に言われてしまった。
「 3本の弦を1度に弾くのは不可能です。 だって弦の高さが、それぞれ違うんですから!!」
ハハハハ・・・・・・。 ちょっと考えれば、そうですよね。
でも、二へドンは、その不可能を可能にするのが超絶技巧だと思い込んでおりましたので・・・・。
では、どうやって、三重音を弾くのか?
例えば、「 ソ・レ・シ 」 の三重音の場合、まず下の音2つ 「 ソ・レ 」を弾いて、
まだ下の音が響いている間に素早く上の音 「 レ・シ 」 を弾くんだそうである。
短い弓幅の間で、素早く移弦するのがコツなんだそうで。
言うのは簡単だが、行なうのは大変なのであ~る。
また家で特訓のタネが増えた・・・・・・・・・・・・・・・。
次に、ハイドンの 「 セレナーデ 」をみてもらう。
レッスンで取り上げるのは今日で3回目だが、今日は初めて、音の強弱をつけてみる。
まずは先生から音の強弱の出し方についてレクチャーを受ける。
mf (メゾフォルテ )は、いつも自分が弾いている音量。 指板と駒の真中辺りで、弓をしっかり弦につける。
f ( フォルテ ) は、mf に圧力を足す。 腕全体の重さを弦にいっぱい乗せる。
力で弾かない事。 力で弾くと、摩擦音が出てしまう。
mp ( メゾピアノ )は、弓の位置は指板側を弾き、弓の指板側の部分の毛を1/2 だけ使う。
つまり弓を向こう側へ倒すような感じに弾く。
強弱のつけ方。
① 弓のスピードが速い。 → 音が強い。
弓のスピードが遅い。 → 音が弱い。
( 圧力の関係もあるので、一概には言えないが、圧力が同じであったら、の条件下で・・・の意味です。以下、同様。)
② 弓の圧力が強い。 → 音が強い。
弓の圧力が弱い。 → 音が弱い。
③ 弓の位置が駒に近い。 → 音が強い。
弓の位置が駒から遠い。 → 音が弱い。
④ 使う弓の毛の量が多い。 → 音が強い。
使う弓の毛の量が少ない。 → 音が弱い。( 音の質が柔らかくなる。
そして、曲によって、この①~④のコンビネーションで、音の強弱をつけて行く。
これを聞いて二へドンは気が遠くなりそうだった。
またコンビネーションかよ!!
不器用な人間に、試練の道は果てしなく続く・・・・・・・・。
2008年01月25日(金)
ヴァイオリン・レッスン48回目。
レッスンを始めて69週目。
今日はいきなり、A線上のセカンド・ポジションの練習に入る。
今まで1年3ヶ月は、ファースト・ポジションばかりやって来たので、新しいポジ
ションに、ついつい身構えてしまう。
今までは、A線上のドは 2の指 ( 中指 ) で弾いていたが、そのポジションを1の
指 ( 人差し指 ) で押さえ、指板を握る様に押さえている親指の位置も一緒にお
引っ越し。
続いて 2、3、4 の指も、1つずつポジションをずらして行く。
セカンド・ポジションで 「 ド・レ・ミ・ファ 」 「 ファ・ミ・レ・ド 」と数
回練習してみた。
生まれて初めてやってみたにしては、まあ、クラスの皆さん全員、上手く出来た
かな?
続いて E線の 「 ソ・ラ・シ・ド 」 「 ド・シ・ラ・ソ 」も練習。
2つを組み合わせて、「 ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド 」 「 ド・シ・ラ
・ソ・ファ・ミ・レ・ド 」と オクターブで練習。
これは、A線もE線も指のF.D.が 1 - 2 - 3・4 なので、スムーズに行った。
ふー。 出だしがこれ位スムーズだと、ポジション移動も何とか、なりそうな気が
してくる……が…。
まだ、ファースト・ポジションでも、♭( フラット ) の付く曲は未習なんだよな
ぁ…。
全部習った日には、かなり頭の中が混乱するだろうなぁ…。
フォーレの「 シチリアーノ 」
生涯の伴侶を置き忘れた女。
ヴァイオリン・アニマルと化す。
二へドンのヴァイオリンの発表会が有るよ~!!
痛い話 〜 杉劇アンサンブル 練習5回目
ヴァイオリンに3日間、漬け込んでみました。
生涯の伴侶を置き忘れた女。
ヴァイオリン・アニマルと化す。
二へドンのヴァイオリンの発表会が有るよ~!!
痛い話 〜 杉劇アンサンブル 練習5回目
ヴァイオリンに3日間、漬け込んでみました。
Posted by ニヘドン at 22:57│Comments(0)
│ヴァイオリンレッスン
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。