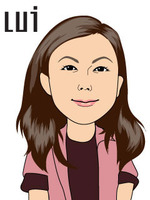2010年05月08日
「 剣岳 ~ 点の記 」 ・ 後編
この記事は「 剣岳 ~ 点の記 」 ・ 前編の続きです。
前編はこちらでお読み下さい。 キャスト等、詳細データ有ります。
→ http://nihedon.hama1.jp/e813869.html
**************************
一行は吹雪に煽られながら馬場島( ばんばじま ) から室堂に戻り
天気の良い青空の下でのんびりしたりする。
かと思うと、再び横殴りの吹雪の中で足を取られながら難儀して歩いたり、
目まぐるしく変わる天候に男達は翻弄される。
浄土山に辿りつくも、雪の為に測量は出来なかった。
一方、下界では山岳会のメンバー達が汽車を降りて来る。
上屋旅館の人が出迎える。
富山日報の記者・牛山明 ( うしやま あきら )が話し掛ける。
「 山岳会の方は随分のんびりとお越しですね。
みんな、測量部が勝つと噂していますよ。 勝算は有るんですか?」
柴崎は今度は人足3人を立山温泉に行かせ、残りの3人は山を登る。
この柴崎の指示に信は不満げな顔を見せる。 「 温泉かよ。」
作業を終えようとすると、雲行きが怪しくなって来る。
測量部隊は吹雪に襲われる。
「 来た時の足跡が無くなっていすぞ!」
長次郎は、「 絶対にここを動かないで下さいよ。」 と言い置いて
1人で道無き道を進んで行く。
長次郎は、牛蛙の様に鳴く雷鳥の姿を見つけ、方角を見極める。
立山温泉は大雨に降り込められる。
竹吉が、下山して来た信達に声を掛ける。
「 信、どうでした? ちゃんとやっていましたか? 」
人夫達は無言で答えない。
柴崎達3人は、天幕まで辿り着く。
長次郎 「 これは季節の変わり目の雨ですちゃ。」
雷鳴が轟き、天幕が飛ばされない様に、3人は外に出て天幕を押さえる。
このままでは天幕ごと飛ぶので、支柱を外して天幕を人間が被って地面にうずくまる3人。
立山温泉から救助隊が出て、3人は助けられる。
旅館で洗濯に励む測量部のメンバー達。
旅館の部屋の柴崎と信の枕元には各自の持ち物が並べて置かれている。
信は熱を出し寝ている。
晴れ間が見える頃、山岳会のメンバー達5人が川原にやって来る。
彼らは 「 室堂に戻り、剣御前( つるぎごぜん )の尾根に戻ろう。」 と
計画を立てた。
雪の斜面を登っている間に、1人のメンバーが斜面を転がり落ちてします。
途中で山岳会のメンバーは猟師2人とすれ違う。
岩の上に熊が姿を現す。
猟師2人が猟銃で熊を撃ち、熊は雪原を滑り落ちて行く。
柴崎「 剣岳って山は、今までの経験と全く違う。」
山岳会のメンバーの1人は、具合が良くない。
ヴィヴァルディの四季「 春 」の第2楽章が流れる。
柴崎の妻の葉津よ( はつよ )は長次郎の妻の宇治佐和に手紙を郵送する。
柴崎達は、次々に三角点を定めて行く。
奥大日岳に櫓を立てる。
山岳会の面々は、垂直に切り立った崖を前に足を止める。
「 念の為にここに1つ天幕を置いて行きましょうか。」
山岳会の小島烏水は双眼鏡で測量隊の隊列を見る。
山岳会の連中は、手旗で柴崎達、測量隊にメッセージを送る。
「 ココカラハ キケン。 ホンジツハ ゲザンス。」
信 「 ご丁寧に教えて下さるってか。」
柴崎と信は、剣岳登頂の決心を固める。
長次郎は動揺の色を見せる。
芝崎達は前剣から登り始める。
山岳会 「 折角昨日教えてやったのに。」
長次郎 「 何れにしても、ここはどうにもならんちゃ。」
途中で柴崎達一行は一休みをする。
長次郎 「 やはり、ここもどうにもならんちゃ。 天気も良くなくなって来たし。」
信 「 柴崎さん。 私にやらせて下さい。」
信は命綱を付けて1人で登るが、足を踏み外して落下してしまう。
信は何とかロープにぶら下がるが、ロープが切れ、雪原を滑り落ちて行ってしまう。
信は命は大丈夫だったが、もう登山は無理な状態になってしまった。
よろけながら歩を運ぶ。
06月28日。 一旦立山温泉に戻る。
測量隊は、突然の下山だったので、宿が取れず、隊員達は旅館の裏庭に
天幕を張って、そこで寝泊りをする事になってしまった。
宿の主人の岡田 「 柴崎、お前はどうして欲しいと思っている?」
そこへ富山日報の記者がやって来る。
「 山岳会は今・・・・・・。」
山岳会の吉田は、膝の古傷が痛む様だ。「 もうこれ以上は無理だろう。」
測量隊の宿泊テントに長次郎の息子がやって来て、食べ物と手紙を託して行く。
食べ物の包みの中身は蒸かした芋だった。
怪我が治った信はが、測量隊のメンバーに合流する。
信は、長次郎の息子から預かった芋を渡す。
又、信は測量隊メンバーの家族から預かって来た手紙を皆に手渡す。
信の奥さんは女の子を無事に産んだという嬉しい知らせも。
測量隊が山で測量をしている所へ山岳会の連中がやって来る。
山岳会の小島烏水は、測量隊の人々に食べ物を振舞う。
柴崎 「 小島さんは何で山に登るんですか? 」
長次郎は、皆が寝静まった後、息子・幸助からの手紙を読みながら涙を流す。
幸助は手紙の中で父にこう綴っていた。「 どんな事があっても登れ。」
翌朝、長次郎は測量隊の人々に向かって言う。
「 雪渓に入ったら山を登るにしても、下りるにしても、
雪を背負い込む形になりますねえ。
山に危険は付き物です。 無理をしても行きましょう。」
三の沢から登る為に歩き始めた5人。
それを見送る山岳会の面々。
音楽はヴィヴァルディの「 四季 」 から♪夏。 ちゃちゃちゃちゃちゃん。
雪渓を抜けた所で、長次郎が腰のロープを解いて
「 ここから先は貴方達が先へ行って下さい。」 と言う。
柴崎 「 いいえ。 私達は仲間です。
長次郎さん。最後まで案内をお願いします。」
♪ ちゃんちゃんちゃんちゃん。
測量隊のメンバー達は頂上に立って声も無く周囲の山並みを見回す。
4等三角点の準備をする。
明治40年07月13日 剣岳頂上に4等三角点を増標する。
その後、長次郎が何かを発見する。
錫杖の先が岩の上に置かれていた。
陸軍測量部の営舎に早速連絡が入る。
「 柴崎からの急電を読みましたでしょうか? 」
「 今度の剣岳の事、それ自体無かった事に出来ないかな?
修験者の錫杖の事なぞ、役に立たない歴史家にでもくれてやればいい。」
下山した柴崎達に大雨が降り注ぐ。
「 初登頂では無かった測量隊 」 の見出しが新聞に載る。
柴崎の妻、葉津よは、その記事が載っている新聞を読む。
見出しは続く。 「 三角点では歴史に残らず 」 「 初登頂は1,000年前 」
葉津よ 「 あなたがどんな事になろうと、葉津よは、あなたの味方です。
元・測量士の古田盛作( 役所広司 )が実に爽やかな笑顔を向ける。
大雨の中で佇む柴崎に富山日報の記者・牛山が傘をさし掛ける。
「 行者が亡くなったそうです。」
08月03日、別山に3等三角点を増標する。
観測中に剣岳山頂に山岳会のメンバー4名が到着する。
「 剣岳初登頂おめでとうございます。
この歴史的登頂に日本登山史に後世まで語り継がれるでしょう。」
小島烏水は手旗でメッセージを送る。
「 生田信( いくた のぶ )、木山竹吉 ( きやま たけきち )、
宮本金作 ( みやもと きんさく )、 岩本鶴次郎 ( いわもと つるじろう )、
山口久右衛門 ( やまぐち きゅうえもん )、 宇治長次郎 ( うじ ちょうじろう )、
柴崎芳太郎 ( しばさき よしたろう )、
剣岳を開山したのは、あなた方です。
ただ地図を作る為だけに自らの仕事を成し遂げた事を心より尊敬します。」
生田信が手旗で返信をする。
「 剣岳登頂おめでとうございます。
小島烏水と山岳会の皆さん、貴方達は私達の掛け替えの無い仲間です。」
「 日本地図は作り上げられた。 彼らを・・・・・・・」 と最後にスーパーが出ます。
文章を全部覚えていないので、知りたい方はDVDを見て下さいませ。
山の映像を背景にエンドロールが流れます。
キャスト名の前に< 仲間たち >という文字が出て来ます。
木村大作監督は撮影にあたってとても厳しかったようですが、
この< 仲間たち >という言葉で、役者さん達の苦労は浮かばれた事と思います。
キャスト名は普通、横書きの映画が多いですが、この映画では縦書きで、
左から右へ流れて行きました。
真っ赤な太陽が映し出されます。
アフリカの輪郭が滲んだ様な太陽も素敵ですが、やっぱり日本の風景が
自分のDNAには合っているなあと思わされました。
エンドロールを見ていると、公式サイトにも取り上げられなかった事が分かる場合も
有ります。立山黒部アルペンルートの名前が出て来ました。
へー。 あそこでも撮影したのかあ。
立山黒部アルペンルートは、二へドンが社会人になった時に初めて母と旅行に行った
思い出の地なのです。
「 原作 新田次郎
この作品を原作者に捧ぐ 」 と最後に出ます。
*********************************
この映画に関する手厳しい批評もいくつか読みました。
でも木村大作だけが100%完璧な映画を作らなければならないって事は無いと思います。
山の峻烈な映像はハッとする程美しいし、仙台フィルの演奏もクラシック・ファンなら
それだけ取り出して聞いても楽しいし。
二へドンは全体的には、この映画を良しとします。
***** 「 「 剣岳 ~ 点の記 」 ・ 後編 」 ・ 完 *******
前編はこちらでお読み下さい。 キャスト等、詳細データ有ります。
→ http://nihedon.hama1.jp/e813869.html
**************************
一行は吹雪に煽られながら馬場島( ばんばじま ) から室堂に戻り
天気の良い青空の下でのんびりしたりする。
かと思うと、再び横殴りの吹雪の中で足を取られながら難儀して歩いたり、
目まぐるしく変わる天候に男達は翻弄される。
浄土山に辿りつくも、雪の為に測量は出来なかった。
一方、下界では山岳会のメンバー達が汽車を降りて来る。
上屋旅館の人が出迎える。
富山日報の記者・牛山明 ( うしやま あきら )が話し掛ける。
「 山岳会の方は随分のんびりとお越しですね。
みんな、測量部が勝つと噂していますよ。 勝算は有るんですか?」
柴崎は今度は人足3人を立山温泉に行かせ、残りの3人は山を登る。
この柴崎の指示に信は不満げな顔を見せる。 「 温泉かよ。」
作業を終えようとすると、雲行きが怪しくなって来る。
測量部隊は吹雪に襲われる。
「 来た時の足跡が無くなっていすぞ!」
長次郎は、「 絶対にここを動かないで下さいよ。」 と言い置いて
1人で道無き道を進んで行く。
長次郎は、牛蛙の様に鳴く雷鳥の姿を見つけ、方角を見極める。
立山温泉は大雨に降り込められる。
竹吉が、下山して来た信達に声を掛ける。
「 信、どうでした? ちゃんとやっていましたか? 」
人夫達は無言で答えない。
柴崎達3人は、天幕まで辿り着く。
長次郎 「 これは季節の変わり目の雨ですちゃ。」
雷鳴が轟き、天幕が飛ばされない様に、3人は外に出て天幕を押さえる。
このままでは天幕ごと飛ぶので、支柱を外して天幕を人間が被って地面にうずくまる3人。
立山温泉から救助隊が出て、3人は助けられる。
旅館で洗濯に励む測量部のメンバー達。
旅館の部屋の柴崎と信の枕元には各自の持ち物が並べて置かれている。
信は熱を出し寝ている。
晴れ間が見える頃、山岳会のメンバー達5人が川原にやって来る。
彼らは 「 室堂に戻り、剣御前( つるぎごぜん )の尾根に戻ろう。」 と
計画を立てた。
雪の斜面を登っている間に、1人のメンバーが斜面を転がり落ちてします。
途中で山岳会のメンバーは猟師2人とすれ違う。
岩の上に熊が姿を現す。
猟師2人が猟銃で熊を撃ち、熊は雪原を滑り落ちて行く。
柴崎「 剣岳って山は、今までの経験と全く違う。」
山岳会のメンバーの1人は、具合が良くない。
ヴィヴァルディの四季「 春 」の第2楽章が流れる。
柴崎の妻の葉津よ( はつよ )は長次郎の妻の宇治佐和に手紙を郵送する。
柴崎達は、次々に三角点を定めて行く。
奥大日岳に櫓を立てる。
山岳会の面々は、垂直に切り立った崖を前に足を止める。
「 念の為にここに1つ天幕を置いて行きましょうか。」
山岳会の小島烏水は双眼鏡で測量隊の隊列を見る。
山岳会の連中は、手旗で柴崎達、測量隊にメッセージを送る。
「 ココカラハ キケン。 ホンジツハ ゲザンス。」
信 「 ご丁寧に教えて下さるってか。」
柴崎と信は、剣岳登頂の決心を固める。
長次郎は動揺の色を見せる。
芝崎達は前剣から登り始める。
山岳会 「 折角昨日教えてやったのに。」
長次郎 「 何れにしても、ここはどうにもならんちゃ。」
途中で柴崎達一行は一休みをする。
長次郎 「 やはり、ここもどうにもならんちゃ。 天気も良くなくなって来たし。」
信 「 柴崎さん。 私にやらせて下さい。」
信は命綱を付けて1人で登るが、足を踏み外して落下してしまう。
信は何とかロープにぶら下がるが、ロープが切れ、雪原を滑り落ちて行ってしまう。
信は命は大丈夫だったが、もう登山は無理な状態になってしまった。
よろけながら歩を運ぶ。
06月28日。 一旦立山温泉に戻る。
測量隊は、突然の下山だったので、宿が取れず、隊員達は旅館の裏庭に
天幕を張って、そこで寝泊りをする事になってしまった。
宿の主人の岡田 「 柴崎、お前はどうして欲しいと思っている?」
そこへ富山日報の記者がやって来る。
「 山岳会は今・・・・・・。」
山岳会の吉田は、膝の古傷が痛む様だ。「 もうこれ以上は無理だろう。」
測量隊の宿泊テントに長次郎の息子がやって来て、食べ物と手紙を託して行く。
食べ物の包みの中身は蒸かした芋だった。
怪我が治った信はが、測量隊のメンバーに合流する。
信は、長次郎の息子から預かった芋を渡す。
又、信は測量隊メンバーの家族から預かって来た手紙を皆に手渡す。
信の奥さんは女の子を無事に産んだという嬉しい知らせも。
測量隊が山で測量をしている所へ山岳会の連中がやって来る。
山岳会の小島烏水は、測量隊の人々に食べ物を振舞う。
柴崎 「 小島さんは何で山に登るんですか? 」
長次郎は、皆が寝静まった後、息子・幸助からの手紙を読みながら涙を流す。
幸助は手紙の中で父にこう綴っていた。「 どんな事があっても登れ。」
翌朝、長次郎は測量隊の人々に向かって言う。
「 雪渓に入ったら山を登るにしても、下りるにしても、
雪を背負い込む形になりますねえ。
山に危険は付き物です。 無理をしても行きましょう。」
三の沢から登る為に歩き始めた5人。
それを見送る山岳会の面々。
音楽はヴィヴァルディの「 四季 」 から♪夏。 ちゃちゃちゃちゃちゃん。
雪渓を抜けた所で、長次郎が腰のロープを解いて
「 ここから先は貴方達が先へ行って下さい。」 と言う。
柴崎 「 いいえ。 私達は仲間です。
長次郎さん。最後まで案内をお願いします。」
♪ ちゃんちゃんちゃんちゃん。
測量隊のメンバー達は頂上に立って声も無く周囲の山並みを見回す。
4等三角点の準備をする。
明治40年07月13日 剣岳頂上に4等三角点を増標する。
その後、長次郎が何かを発見する。
錫杖の先が岩の上に置かれていた。
陸軍測量部の営舎に早速連絡が入る。
「 柴崎からの急電を読みましたでしょうか? 」
「 今度の剣岳の事、それ自体無かった事に出来ないかな?
修験者の錫杖の事なぞ、役に立たない歴史家にでもくれてやればいい。」
下山した柴崎達に大雨が降り注ぐ。
「 初登頂では無かった測量隊 」 の見出しが新聞に載る。
柴崎の妻、葉津よは、その記事が載っている新聞を読む。
見出しは続く。 「 三角点では歴史に残らず 」 「 初登頂は1,000年前 」
葉津よ 「 あなたがどんな事になろうと、葉津よは、あなたの味方です。
元・測量士の古田盛作( 役所広司 )が実に爽やかな笑顔を向ける。
大雨の中で佇む柴崎に富山日報の記者・牛山が傘をさし掛ける。
「 行者が亡くなったそうです。」
08月03日、別山に3等三角点を増標する。
観測中に剣岳山頂に山岳会のメンバー4名が到着する。
「 剣岳初登頂おめでとうございます。
この歴史的登頂に日本登山史に後世まで語り継がれるでしょう。」
小島烏水は手旗でメッセージを送る。
「 生田信( いくた のぶ )、木山竹吉 ( きやま たけきち )、
宮本金作 ( みやもと きんさく )、 岩本鶴次郎 ( いわもと つるじろう )、
山口久右衛門 ( やまぐち きゅうえもん )、 宇治長次郎 ( うじ ちょうじろう )、
柴崎芳太郎 ( しばさき よしたろう )、
剣岳を開山したのは、あなた方です。
ただ地図を作る為だけに自らの仕事を成し遂げた事を心より尊敬します。」
生田信が手旗で返信をする。
「 剣岳登頂おめでとうございます。
小島烏水と山岳会の皆さん、貴方達は私達の掛け替えの無い仲間です。」
「 日本地図は作り上げられた。 彼らを・・・・・・・」 と最後にスーパーが出ます。
文章を全部覚えていないので、知りたい方はDVDを見て下さいませ。
山の映像を背景にエンドロールが流れます。
キャスト名の前に< 仲間たち >という文字が出て来ます。
木村大作監督は撮影にあたってとても厳しかったようですが、
この< 仲間たち >という言葉で、役者さん達の苦労は浮かばれた事と思います。
キャスト名は普通、横書きの映画が多いですが、この映画では縦書きで、
左から右へ流れて行きました。
真っ赤な太陽が映し出されます。
アフリカの輪郭が滲んだ様な太陽も素敵ですが、やっぱり日本の風景が
自分のDNAには合っているなあと思わされました。
エンドロールを見ていると、公式サイトにも取り上げられなかった事が分かる場合も
有ります。立山黒部アルペンルートの名前が出て来ました。
へー。 あそこでも撮影したのかあ。
立山黒部アルペンルートは、二へドンが社会人になった時に初めて母と旅行に行った
思い出の地なのです。
「 原作 新田次郎
この作品を原作者に捧ぐ 」 と最後に出ます。
*********************************
この映画に関する手厳しい批評もいくつか読みました。
でも木村大作だけが100%完璧な映画を作らなければならないって事は無いと思います。
山の峻烈な映像はハッとする程美しいし、仙台フィルの演奏もクラシック・ファンなら
それだけ取り出して聞いても楽しいし。
二へドンは全体的には、この映画を良しとします。
***** 「 「 剣岳 ~ 点の記 」 ・ 後編 」 ・ 完 *******
2010年05月08日
プラメナ・マンゴーヴァ先生のマスタークラス
 ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2010
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2010無料イベント
2010年05月03日(月・祝)
会場 : G610 < エルスネル >
09:30 ニヘドンが並び始めました。
10:00 開場。
10:30 開演。
きつめにパーマを掛けた金髪のロングヘアのプラメナ・マンゴーヴァ先生が、
「 オハヨウゴザイマース。」と日本語で言いながら、にこやかに部屋に入って来ました。
今日の生徒は男子音大生。
曲はシューマンの「 謝肉祭の道化 」第1曲。
先ずは生徒が最初から最後まで通して弾いてみます。
ニヘドンの感想。
「 ん−。楽譜通りに弾いているんだろうけれど、頭で考えちゃってて、心が伝わって来ない。
全体的に単調な感じ。」
マンゴーヴァ先生( 次からは略してMと表記します。)
「 アリガトウゴザイマス。
Very good work.」以降、M先生が英語でアドバイスした物を逐次通訳者が日本語にしたものを表記して行きますね。
「 ピアノ的に頑張って弾いた事がよく分かりました。
Bravo !
今、足りないもの、今日、焦点を当てたいものは、この音楽の背景です。
謝肉祭、フェスティバル、そのフィーリングが無かったですね。
ドラマトゥルギー的にと申しましたが、謝肉祭の1つ1つの仮面を被っている、その雰囲気なんです。
小さいパーツをどう組み立てて大きな全体にして行くか。
Musical speaking 、パーツの移動がぎこちなくて説得力が無い。
演奏は良い傾向に有りますし、各パーツは正しいので、スープの各種スパイスを馴染ませて行きましょう。
ではもう1回最初から弾いて下さい。」
学生君はもう1回最初から弾きます。
M先生が途中でストップをかけます。
「 冒頭は今ちょっと元気が無い。
朝の5時まで飲んでいて、まだエンジンが掛かっていないみたいですね。」
M先生が演奏の見本を見せてくれます。
『 おお! 正に festival だ!! 』
ニヘドンはマスタークラスを聴講するのが大好きです。
と言うのも、演奏家が何を考えてその曲を弾くのかが、よく分かるからです。
勿論、雑誌のインタビュー等で、演奏家の考え方が分かる場合も有りますが、マスタークラスの場合は、1つの曲を部分部分に分割して、その部分をどの様に考えて弾くかと言うのが具体的に分かるからです。
またM先生の様に実際に弾いてくれる先生だと、生徒との演奏の違いが如実に現れ、プロの演奏家のプロたるゆえんを思い知らされます。
「 この曲はウィーンの作品なんです。
ウィーンのリズムと言いますか、そう言うものも感じなくてはなりません。
全く違う仮面を被るんです。
上の旋律の方がもっと聞こえて来る様に。
I have a question for him.
最後の4つのアクセントはどこに有るのかしら?
書いて無いですね。もっと高貴な感じで。」
又M先生が見本に弾きます。
「 pedalization ( ペダライゼイション ) は非常にナイーブだけど優美な感じで。
今、全部にペダルを掛けてしまっているんですね。
クレッシェンドと共にペダルを増やして行く。」
M先生は生徒の背中を指で触わってタッチを教えます。
「 右手の小指の部分が音を当てるのが足らないんです。
何かこう緊張していると言うか、もっと全開で、自分を全開にして。
He is waiting for the next.
なので、1つの考え方としては、音楽は流れているのです。
もっとノスタルジックな感じで。
1小節ずつ見ないで。 少なくとも2小節ずつ見て。」
M先生の見本の時間です。
( あー、本当だあ〜! )
M先生が言わんとしている事が、きちんと音に現れています。
うむむむむ…。
良い演奏家が必ずしも良い教師になれる訳では無いけれども、マンゴーヴァ先生は、凄く教える技術を持っていると感じました。
「 シューマンの書き方なんですけど、左手が右手の真似、右手が左手の真似なんです。
彼の左手は今、音楽に参加していないんです。
His music doesn't speak.
内面からもうちょっとagressive に。」
M先生が見本を見せます。
「 Much more deeper emotion.
スープとかカルボナーラとか、ぐちゃぐちゃになってます。
Posted by ニヘドン at
14:11
│Comments(0)